相続のための土地評価入門【第1回】土地が持つ5種類の評価価格と地目分類
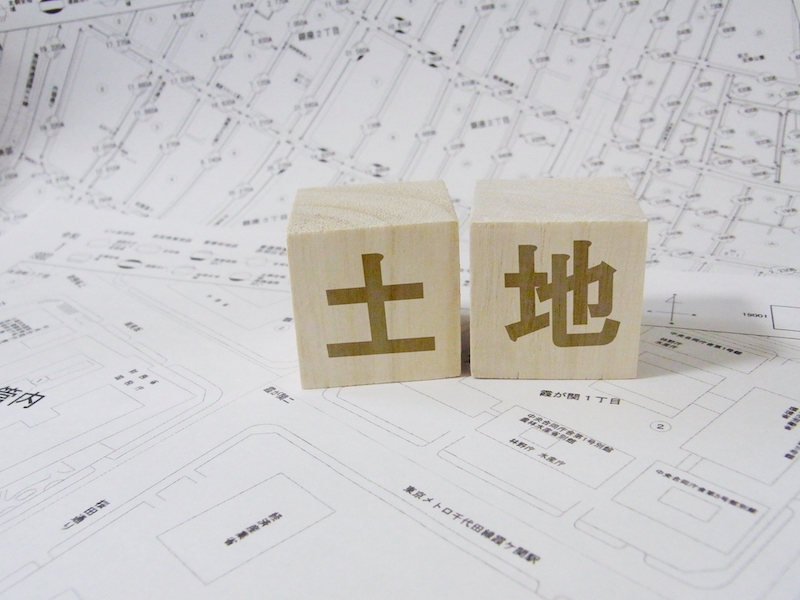
こんにちは、相続専門の税理士法人ともに編集部統括ライターの佐藤です。
相続や贈与で引き継ぐ財産のうち最も価格が高いのは、一般的には土地などの不動産です。
そこで、シリーズ記事『相続のための土地評価入門』を作成しました。土地の評価方法を全7回で紹介します。
土地の評価について知りたい方はぜひお読みください。土地評価で必要な知識が身につきます。
1.土地の評価が難しい理由
まずはじめに、土地の評価が難しい理由からお伝えします。
1-1.理由1. 土地の形が一定ではないから
土地評価が難しい理由は、所在地や道路との位置関係や形状が千差万別で、全く同じものが存在しないことにあります。
もし、評価するのが以下のような土地なら、財産評価額の計算は非常に簡単です。
【評価がカンタンな土地】
・市街地にある
・正面のみが道路に面している
・単純な正方形の宅地
しかし、実際には上記のような条件を持つ土地はほとんどありません。
・複雑な形状の土地
・傾斜地に存在する土地
・道路に面していない土地
といった、簡単には評価計算できない土地の方が多いです。
1-2.理由2.土地の利用目的が異なるから
土地の利用目的が変われば評価も変わります。土地の評価額が複数種類存在するのはそれが理由です。
公的なものだけでも、5種類の評価があります。つぎからは、公的に認められた5つの土地評価について解説します。
2.公的な土地評価5種
それでは、以下5種類の土地の公的価格をご紹介します。
・固定資産税評価額
・路線価
・実勢価格
・公示地価
・基準地価
相続税や贈与税の計算で使うのは、上記のうち固定資産税評価額と路線価です。ただし例外的に実勢価格を使うこともあります。(一定の要件を満たす場合)
それでは、土地の5種類の公的評価について順番に解説していきます。
2-1.公的な土地評価その1.固定資産税評価額
はじめに「固定資産税評価額」を解説します。固定資産税評価額は、相続税や贈与税の計算でも使われる土地の評価価格です。
固定資産税評価額は、固定資産評価基準に基づいて決定されます。
固定資産評価基準とは、毎年の固定資産税を決めるためのベースとなるもので、市区町村ごとに変わります。
固定資産税評価額は、法で定められた固定資産評価基準にもとづき、土地や建物が登記されるたびに、各自治体の固定資産評価員が1軒ずつ確認して決めています。
・地域の特性(市街化区域や市街化調整区域か)
・土地の形状(どのように道路に接しているか)
・面積
といった、それぞれの土地の持つ属性から評価を決めているのです。
さらに固定資産税評価額は公示価格の約70%が目安とされます。そのため所有する土地の固定資産税評価額を知るには、公示価格✕0.7 という計算式で概算を計算可能です。
ちなみに、土地の公示価格は毎年1月1日に決定されます。また固定資産税評価額は原則的に3年に1回のペースで見直しが行われます。
ちなみに、土地・家屋を所有されている方であれば、毎年5月ごろに届く固定資産税の課税明細書に固定資産税評価額の記載があります。
2-2.公的な土地評価その2.路線価
つづいて「路線価」について解説します。路線価は、道路に面した土地に対して付けられる価格です。
毎年1月1日を基準の日とし、7月に国税庁が路線価を発表します。路線価は、公示価格の80%程度を目安に決定されています。
2-3.公的な土地評価その3.実勢価格
実勢価格とは、買い手と売り手の交渉の結果、実際に土地の売買取引が成立した価格のことを指します。売買価格と言いかえても良いでしょう。
私たちが土地の価値を考えるときにイメージするのが実勢価格です。実勢価格は路線価の1.25倍程度が目安になります。
2-4.公的な土地評価その4.公示地価
公示地価は、地価表示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が公表する土地の目安価格です。
毎年1月1日を基準日とし、標準地の正常な価格を3月に公示価格として発表します。
公示地価を発表する目的は、「適正な地価の形成」です。詳しく説明すると、以下の5つの目的があります。
適性な地価形成が目的なので、公示地価は実勢価格に近い金額で発表されることが多いです。
そのため、実際に土地の売買取引をする際の目安として使えます。
2-5.公的な土地評価その5.基準地価
基準地価とは、都道府県が調査した土地の目安価格のことです。
基準地価には公示地価を補完する役割があります。その理由は、公示地価が全国すべてのエリアを網羅していないからです。
したがって、基準地価と公示地価をあわせて見ることで、実勢価格に近い土地の価格が把握できます。
また、基準地価の調査タイミングは公示地価とは異なっています。そのため、両者を比較すれば、地価の変化もつかめるでしょう。
つづいて「地目」を解説します。
3.地目(土地の種類)
ここからは「地目」の解説をします。
地目を解説する理由は、相続税と大きく関わりがあるからです。
相続税における財産評価の指標である「財産評価基本通達」では、土地を以下の9種類に分類しています。
【地目9種】
・宅地
・田
・畑
・山林
・原野
・牧場
・池沼
・鉱泉地
・雑種地
以上の9区分を地目(ちもく)と呼びます。地目は、公平な課税を実現するために作られました。
たとえば、条件が以下のように全く同じ2つの土地があったとします。
【土地の条件】
・同じ町内にある
・隣あっている
・面積が同じ
・形も同じ
しかし、上記の土地の利用目的は以下のように異なっています。
【土地の利用目的】
・宅地
・畑
片方が「宅地」で、もう片方は「畑」です。
このように利用目的と地目が異なる土地を、同じように評価するわけにはいきません。なぜなら、土地の利用状況や財産価値を適切に反映していないような評価額を元にしてしまうと、公平な課税ができないからです。
3-1.土地の利用目的を考慮するために地目がある
土地の利用目的を考慮せずに課税額を決めると、税の公平性に問題があります。
そこで、財産評価基本通達は9種類の地目を定めました。地目により、評価方法変更することで、公平性の問題に対処したのです。
3-2.地目分類はここを見ればわかる
地目の種類は「不動産登記規則」第99条で定められています。
不動産登記に関する手続きが記載された「不動産登記事務取扱手続準則」の第68条と第69条に、具体的な分類方法が記されています。
以下が、地目分類のもとである不動産登記事務取扱手続準則 第68条です。
地目は9つなのに規定は23種類あります。その理由と、各地目ごとの具体的な評価方法を第2回以降で解説します。
お電話でのご相談
上記フリーダイヤルまでお気軽にお電話ください。
(スマートフォンの方はアイコンをタップして発信)
メールでのご相談
お悩み・ご状況をお知らせください。
担当者より平日の2営業日以内に連絡いたします。
オンラインでの面談
オンラインツールを使用した面談も可能です。
まずはこちらからお問い合わせください。


