小規模宅地等の特例で駐車場の相続税が安くなる?相続専門税理士が解説

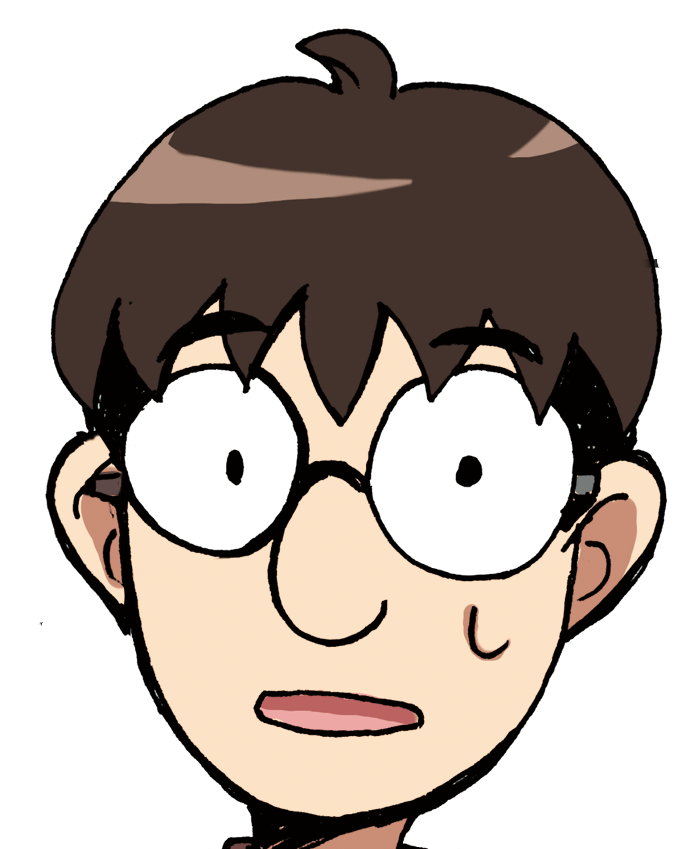
入江先生!僕、駐車場を相続することになりました!
それで、『小規模宅地等の特例』を適用すると相続税が8割安くなると聞いたんですけど、本当ですか?

初めての相続なのに詳しいですね!
はい、確かに小規模宅地等の特例を使えると税金が減額されて、ぐっと相続税が下がります。
ただ駐車場の場合、8割減額されることはないと思った方がいいです。
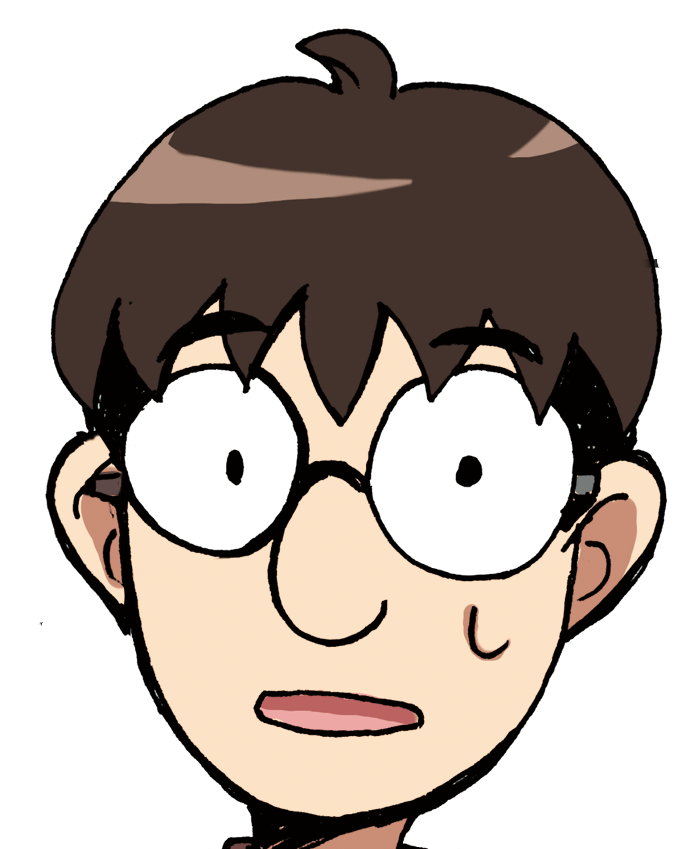
えっ!そうなんですか?ショックだなあ。

駐車場の場合は、状況によりますが、50%の減額なら可能かもしれません。
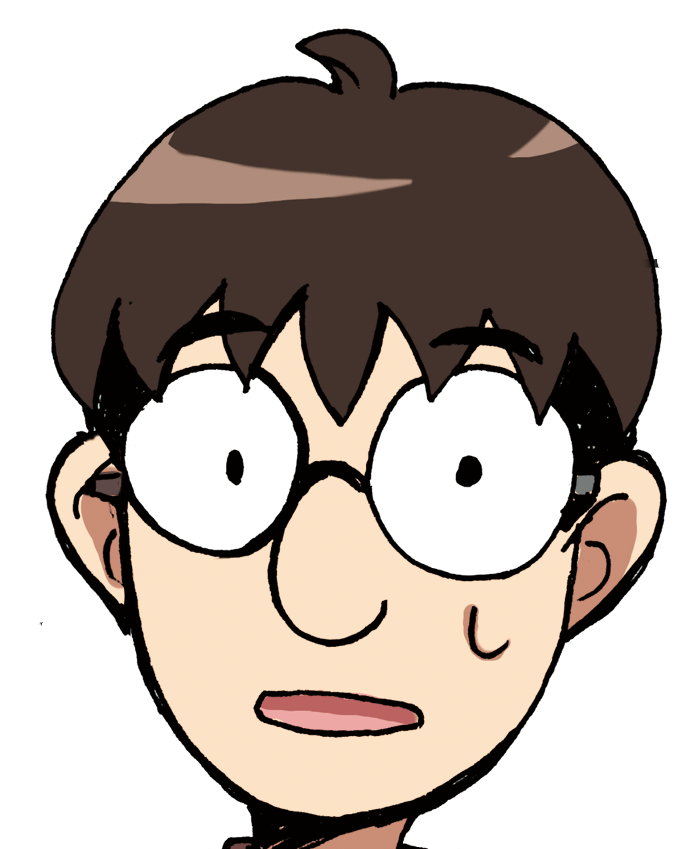
本当ですか?50%でも税金が安くなるなら大助かりです。詳しく教えて下さい、先生!
小規模宅地等の特例は、適用できると相続人にとって大きな節税効果が得られる税金減額の手段です。
この記事では、駐車場を相続する方が、小規模宅地等の特例を適用してなるべく納税額を安く抑える方法を、やさしく解説いたします。
駐車場の形の宅地を相続される可能性がある方はぜひお読みください。
駐車場は小規模宅地等の特例の減額対象
被相続人が経営していた月極駐車場、コインパーキングなどの賃貸駐車場は、小規模宅地等の特例が適用できる可能性がある、減額対象の土地です。(小規模宅地等の特例についてはこちらの記事で詳しく解説しています。)
小規模宅地等の特例が適用できる宅地の種類は、4つあります。事業経営されている駐車場は、4種のうち「貸付事業用宅地」にあたります。
駐車場は貸付事業用宅地として減額50%
貸付事業用宅地等の税金の減額割合は50%です。事業経営の駐車場は貸付事業用宅地等に該当し、相続時の減額割合は50%になります。
小規模宅地等の特例には、事業用地でも80%減額できる「特定事業用宅地等」という分類の宅地があります。しかし駐車場用地はこの分類に該当しません。事業用の駐車場は貸付事業用宅地になります。しががって80%減額は適用できず、50%減額になります。
小規模宅地等の特例を適用できない駐車場とは
駐車場の作り方や状況によっては貸付事業用宅地とみなされないことがあります。貸付事業用宅地にならない場合は特例が適用できません。その結果減額できない‥ということもあります。
どのような駐車場だと特例が適用できなくなるのか、まずはNGな駐車場からご説明します。
適用できない例1 土地上に構築物がない青空駐車場
土地の上に構築物がない青空駐車場は特例を適用できません。貸付事業用宅地等を使った小規模宅地等の特例適用は「土地の上に構築物がある」宅地に対してのみ、認められるからです。
土がむき出しで、ロープで仕切っただけ‥といった状態の駐車場は「構築物がある土地」にはなりません。ロープはすぐに取り除けますし設置するための費用もかからないからです。これらは構築物とはみなされません。
すぐできる簡素な加工しかしていない青空駐車場は特例の対象にはなりません。
適用できない例2 無償または低価格で貸し出している
駐車場の状態が問題なかったとしても、有償で貸し出していない場合は対象外です。
たとえば無償または社会通念上あり得ない低価格で、親族やそれ以外の人に貸し出しているような場合は特例を適用できません。きちんと対価を受け取っていないため、「業」として運営していない‥とされるからです。
適用できない例3 一角に自家用車を駐車している
経営する有料駐車場の一角に自家用車を駐車していると、その部分は貸付事業用宅地等とは認められず、減額対象から除かれます。
特例が適用できない駐車場の例をご紹介してまいりました。
つづいて特例を適用可能な駐車場の事例をご紹介します。
小規模宅地等の特例を適用できる駐車場
それでは、小規模宅地等の特例が適用可能な貸付事業用宅地に該当する駐車場の条件をご紹介します。
基本的に、土地の上に「構築物」が構築されていれば対象になります。
適用できる例1 アスファルトで舗装された駐車場
アスファルトで舗装された駐車場は特例の対象です。
適用できる例2 砂利を敷いた駐車場
砂利敷きの駐車場は特例の対象です。なぜなら砂利を敷くことにも費用や工数がかかるからです。その状態に整えるため費用をかけたことは、「構築物を構築した」と認められる条件になります。
適用できる例3 コインパーキング式駐車場
時間貸し可能なコインパーキング式駐車場は特例対象です。コインパーキング設備の所有者がコインパーキング業者で、設備を借りて営業している場合も問題はありません。小規模宅地等の特例の対象として認められます。
適用できる例4 タワー式駐車場
スペースを有効に活用するため、タワー式にした駐車場も貸付事業用宅地として特例の対象になります。土地の上に「構築物がある」ので条件を満たしています。
【例外:自宅敷地内の自家用駐車場は80%減額の対象】
貸出事業用の駐車場は50%減額の対象と解説して来ました。ただ同じ駐車場でも、自家用車を自宅敷地内の駐車スペースに駐めている場合は、そのスペースは居住用宅地にみなされます。居住用宅地の場合は減額80%ですから、同じ駐車場でも自宅敷地の自家用車の駐車場は、80% 減額になるというわけです。
相続税対策で新規の駐車場建設はおすすめしない
ここで注意事項です。貸付事業用の駐車場が、条件を満たせば相続税の減額50%の対象になると知って、節税のために駐車場を建設しようと考える方がおられます。
しかし相続税の節税目的での駐車場建設はおすすめできないです。
なぜなら、相続発生前の3年以内に取得した土地には小規模宅地等の特例が適用されないからです。税金が減額されません。
また事業についても、相続発生前の3年以内に新たに宅地を事業用途に使い始めたものは、小規模宅地等の特例の対象となりません。平成30年度の税制改正で、このように取り決められました。
相続が始まることが予測できてから、駐車場などを購入したり、保有している土地に駐車場を建設したりしても、特例は適用できない確率が高いということです。これが節税の手段として駐車場を作るのはおすすめできない理由です。
減額50%を適用できる相続人の条件
さて、相続する「人」の方にも特例適用の条件があります。
駐車場を相続した相続人が、減額50%を受けるための「相続人側」の条件を解説します。以下の3点です。
減額50%を受ける相続人側の条件
・相続後も引き続き駐車場経営を続ける
・相続税の申告期限までに駐車場を売却しない
・駐車場は、相続の3年以上前から経営している
土地と人、両方が特例適用のための条件を満たしていないと、税金の減額を受けることはできないのです。小規模宅地等の特例を解説したこちらの記事でも、要件を詳しくご紹介しています。併せてお読みください。
まとめ
駐車場を相続するとき、小規模宅地等の特例を適用して税金を減額できるのはどんな駐車場かについて、解説しました。
駐車場の状況により、特例を適用できる駐車場、できない駐車場があり、それぞれの特徴を詳しく解説しています。
特例は「宅地」に対して適用されるものなので、駐車場の上に構築物があることが基本的な条件です。
小規模宅地等の特例対象は、駐車場用地である「貸付事業用宅地」の他に、80%減額できる特定居住用宅地等、特定事業用宅地等などがあります。
小規模宅地等の特例を使えるかどうかや、直接税理士と話をしてみたい方は、無料相談をご利用ください。初回無料となっております。
お電話でのご相談
上記フリーダイヤルまでお気軽にお電話ください。
(スマートフォンの方はアイコンをタップして発信)
メールでのご相談
お悩み・ご状況をお知らせください。
担当者より平日の2営業日以内に連絡いたします。
オンラインでの面談
オンラインツールを使用した面談も可能です。
まずはこちらからお問い合わせください。


